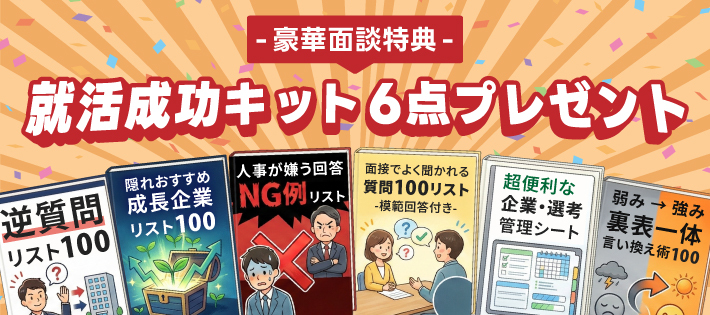記事一覧
全て
マナー
説明会
ES対策
面接対策
親対策
自己分析
市況分析
イベント
長期インターン
短期インターン
ビジネススキル
履歴書
業界・企業分析
ガクチカ
自己PR
志望動機
グループディスカッション
スタートアップ
OB訪問
-
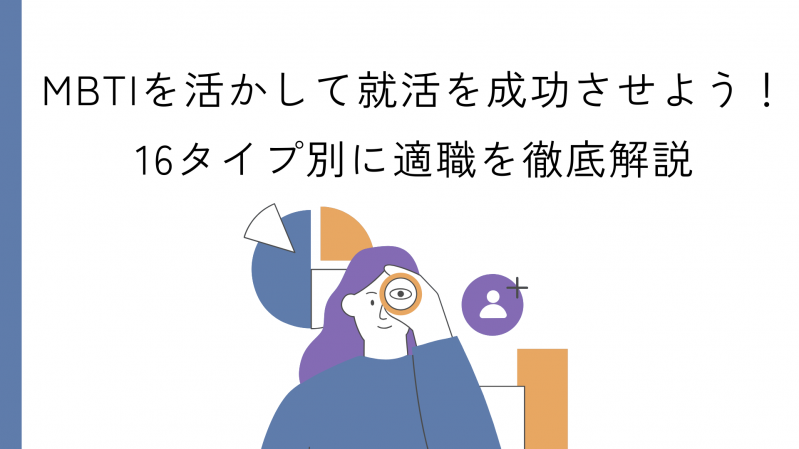 マナー公開日:2025年08月28日 更新日:2025年12月15日MBTIを活かして就活を成功させよう!16タイプ別に適職を徹底解説
マナー公開日:2025年08月28日 更新日:2025年12月15日MBTIを活かして就活を成功させよう!16タイプ別に適職を徹底解説 -
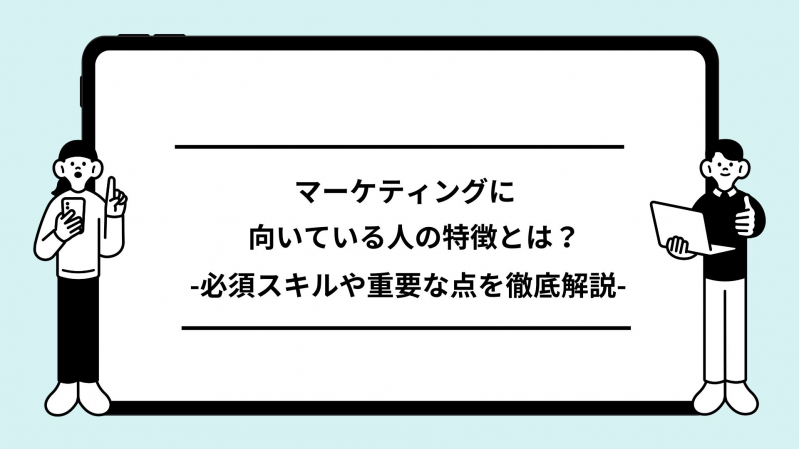 マナー公開日:2025年07月11日 更新日:2025年12月15日マーケティングとはどんな仕事?就活生向けに解説!向いている人の特徴も紹介
マナー公開日:2025年07月11日 更新日:2025年12月15日マーケティングとはどんな仕事?就活生向けに解説!向いている人の特徴も紹介 -
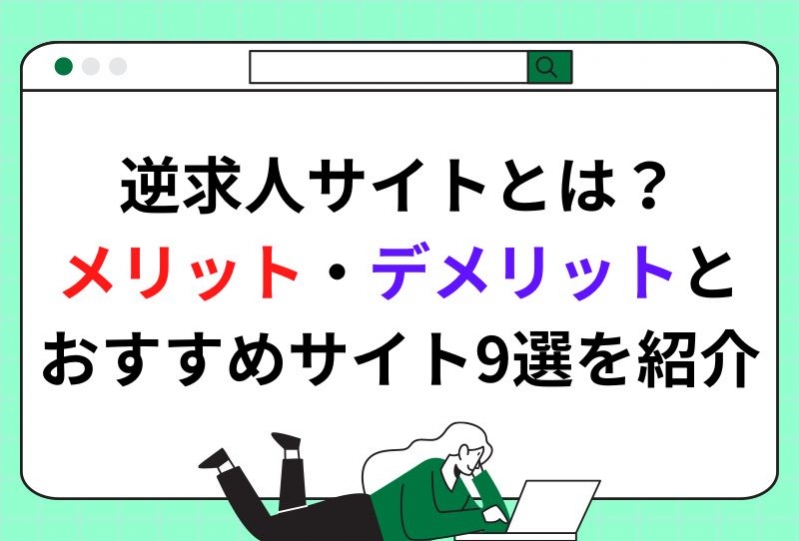 市況分析公開日:2023年11月11日 更新日:2025年12月15日【最新版】逆求人サイトのおすすめ9選!オファーを貰うコツも紹介
市況分析公開日:2023年11月11日 更新日:2025年12月15日【最新版】逆求人サイトのおすすめ9選!オファーを貰うコツも紹介 -
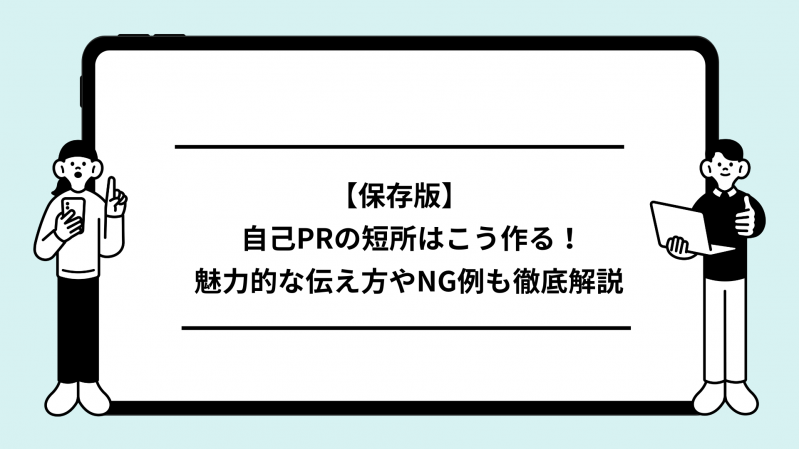 マナー公開日:2025年09月01日 更新日:2025年12月10日【保存版】自己PRの短所はこう作る!魅力的な伝え方やNG例も徹底解説
マナー公開日:2025年09月01日 更新日:2025年12月10日【保存版】自己PRの短所はこう作る!魅力的な伝え方やNG例も徹底解説 -
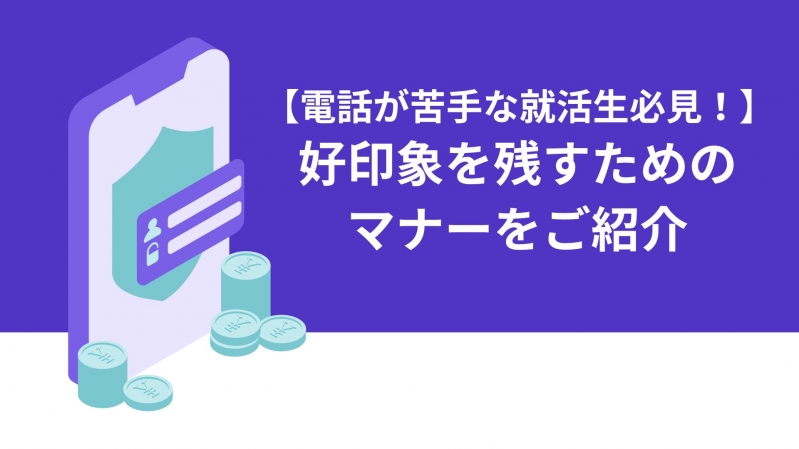 マナー公開日:2022年08月08日 更新日:2025年12月09日【電話が苦手な就活生必見】基本のマナーやポイントを紹介
マナー公開日:2022年08月08日 更新日:2025年12月09日【電話が苦手な就活生必見】基本のマナーやポイントを紹介 -
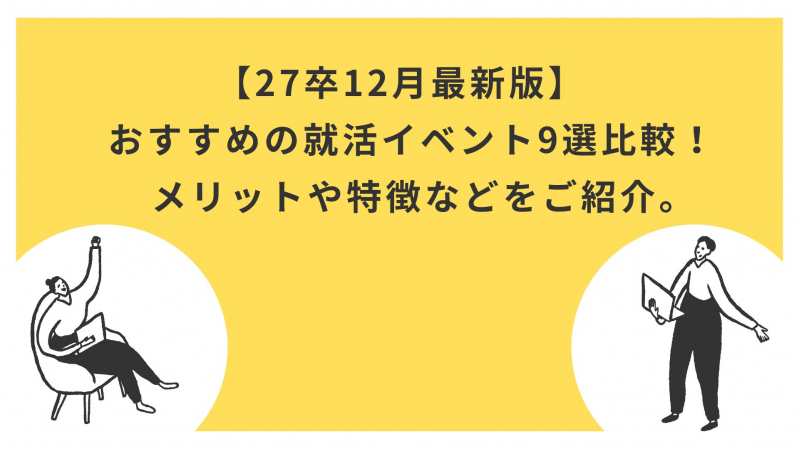 説明会公開日:2024年06月13日 更新日:2025年12月04日【27卒最新版】12月におすすめの就活イベント9選比較!メリットや特徴などをご紹介。
説明会公開日:2024年06月13日 更新日:2025年12月04日【27卒最新版】12月におすすめの就活イベント9選比較!メリットや特徴などをご紹介。 -
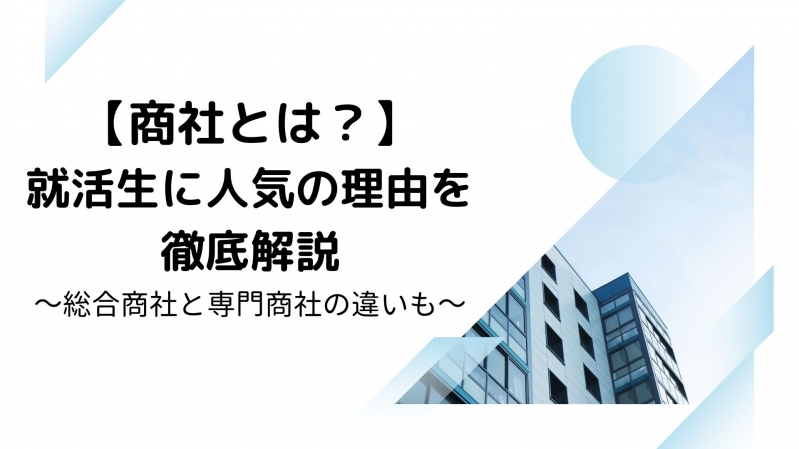 市況分析公開日:2022年08月08日 更新日:2025年10月27日商社とは?人気の理由や向いている人の特徴を解説!総合商社と専門商社の違いも
市況分析公開日:2022年08月08日 更新日:2025年10月27日商社とは?人気の理由や向いている人の特徴を解説!総合商社と専門商社の違いも -
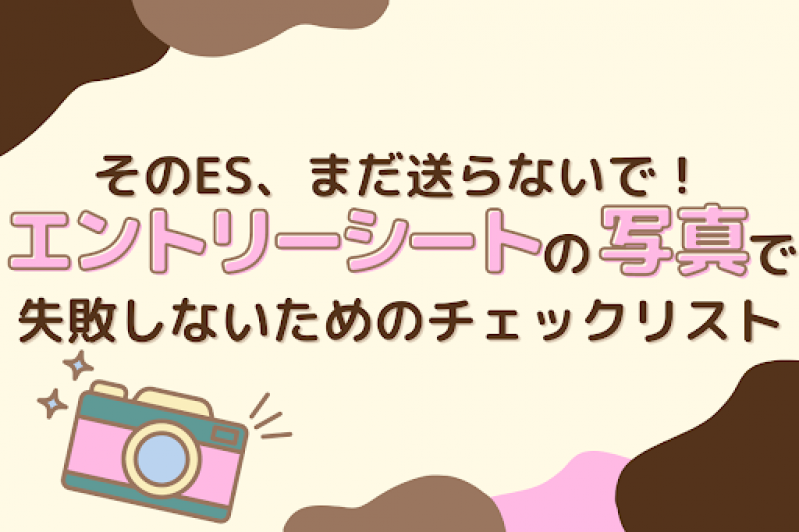 ES対策公開日:2023年01月16日 更新日:2025年10月22日エントリーシートの写真で失敗しないためのチェックリスト
ES対策公開日:2023年01月16日 更新日:2025年10月22日エントリーシートの写真で失敗しないためのチェックリスト -
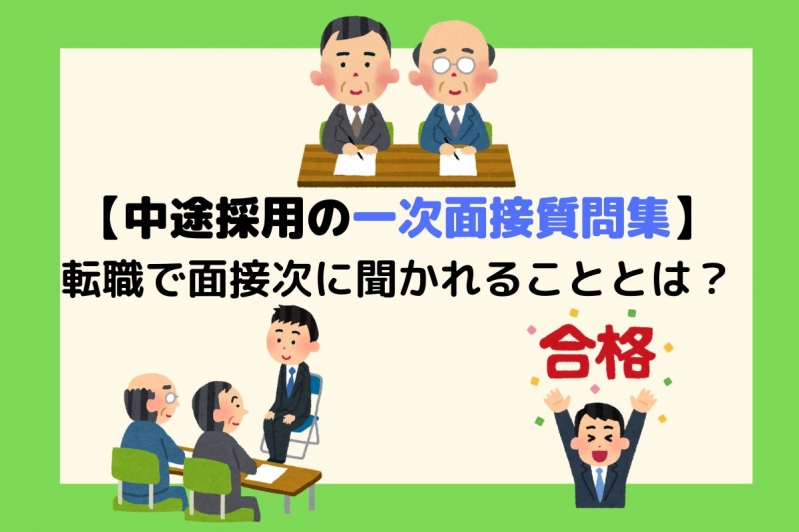 面接対策公開日:2020年06月16日 更新日:2025年10月22日【中途採用の一次面接質問集】 転職で面接次に聞かれることとは?
面接対策公開日:2020年06月16日 更新日:2025年10月22日【中途採用の一次面接質問集】 転職で面接次に聞かれることとは? -
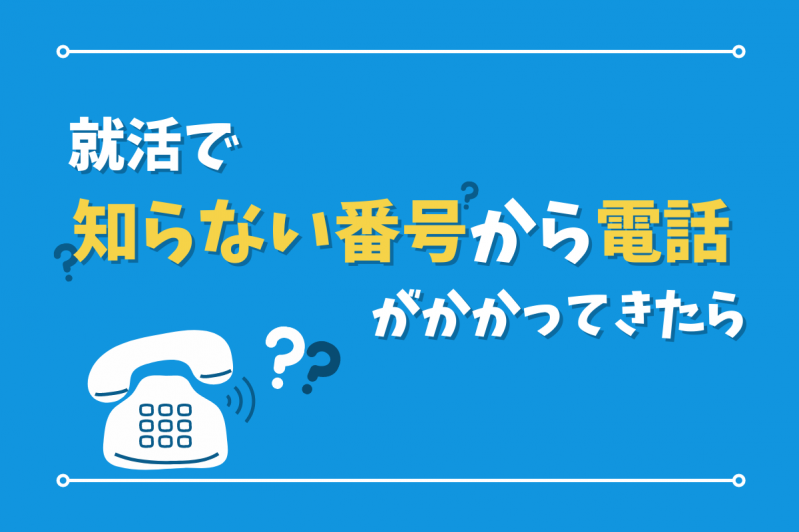 マナー公開日:2022年08月08日 更新日:2025年10月22日【例文付き】就活で知らない番号から電話がかかってきたら...
マナー公開日:2022年08月08日 更新日:2025年10月22日【例文付き】就活で知らない番号から電話がかかってきたら... -
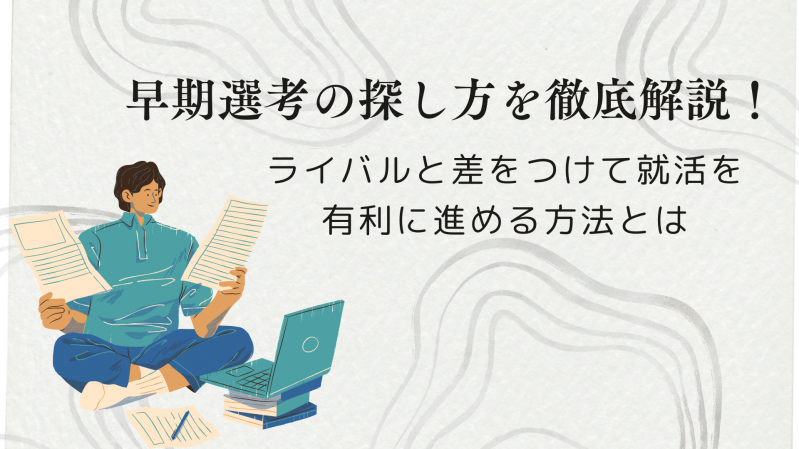 マナー公開日:2023年12月08日 更新日:2025年10月20日早期選考の探し方を徹底解説!ライバルと差をつけて就活を有利に進める方法とは
マナー公開日:2023年12月08日 更新日:2025年10月20日早期選考の探し方を徹底解説!ライバルと差をつけて就活を有利に進める方法とは -
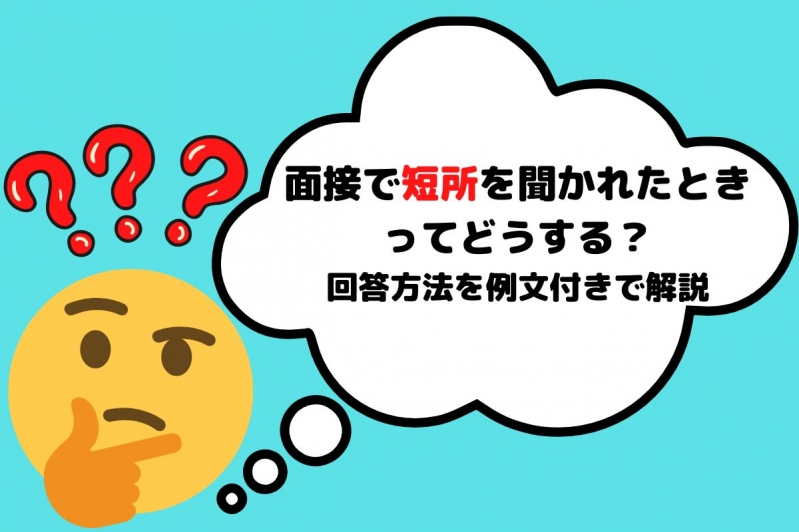 面接対策公開日:2023年01月26日 更新日:2025年10月08日面接で短所を聞かれたときってどうする?回答方法を例文付きで解説
面接対策公開日:2023年01月26日 更新日:2025年10月08日面接で短所を聞かれたときってどうする?回答方法を例文付きで解説