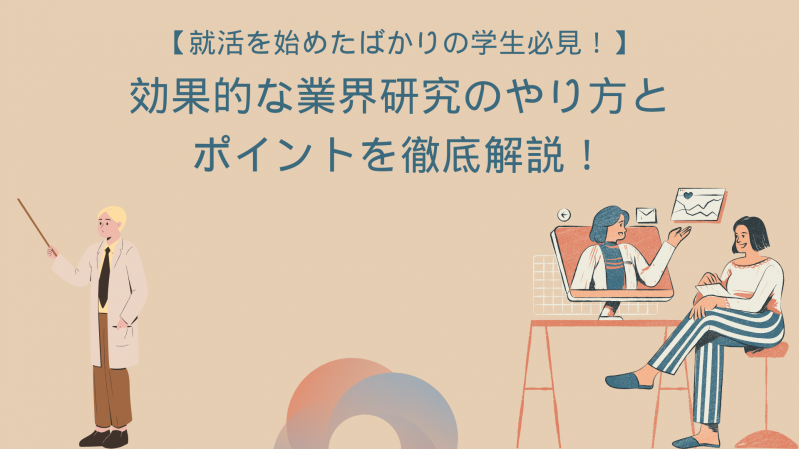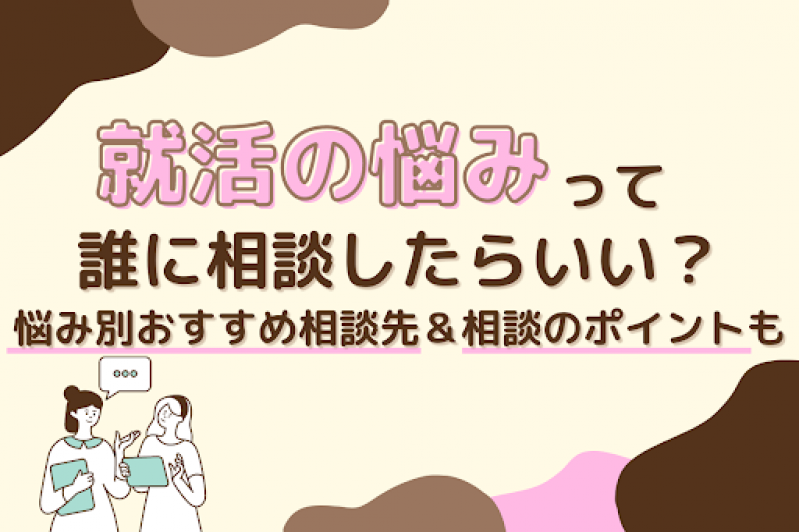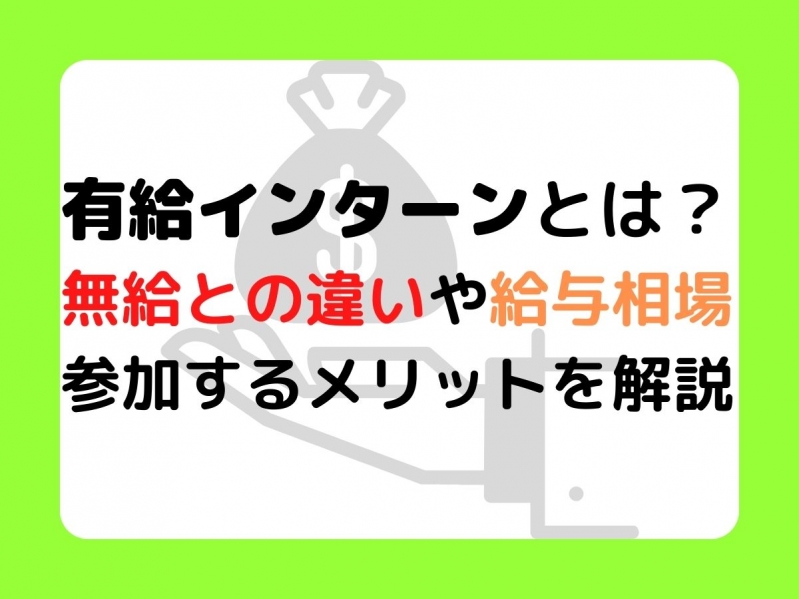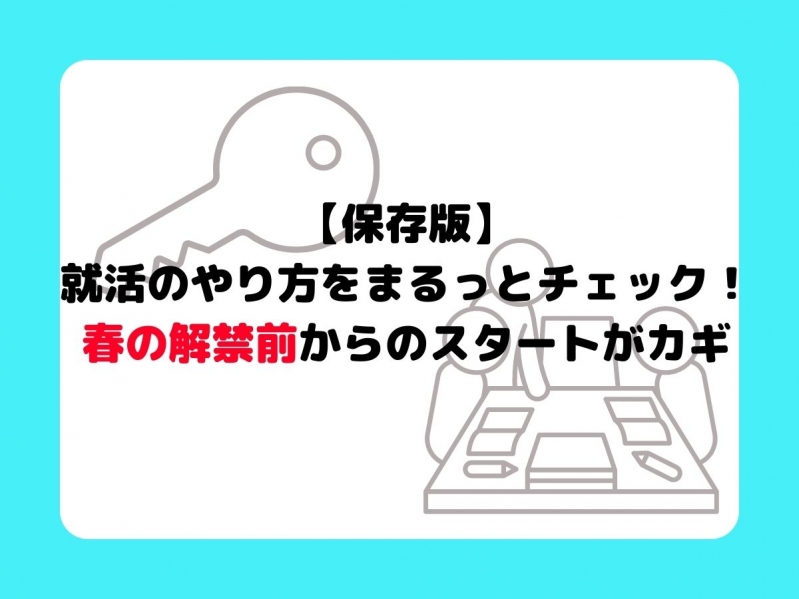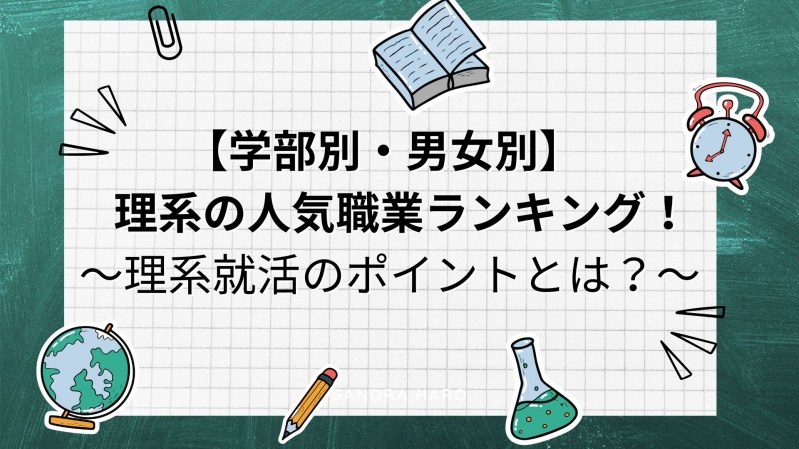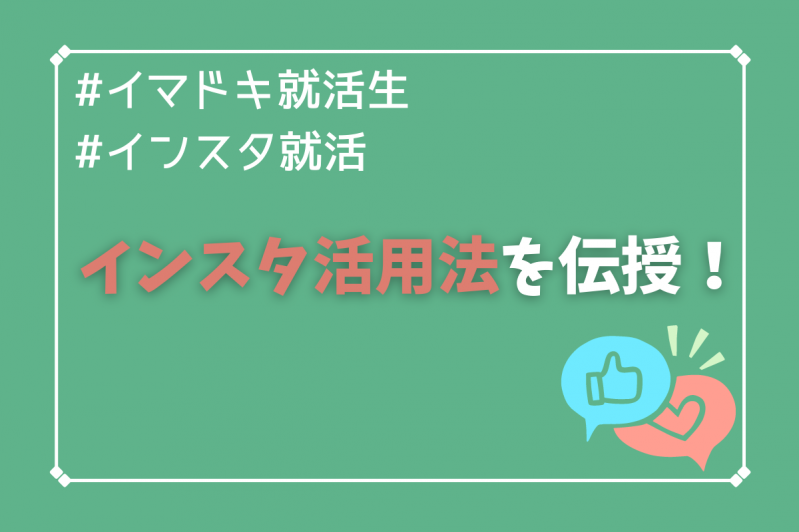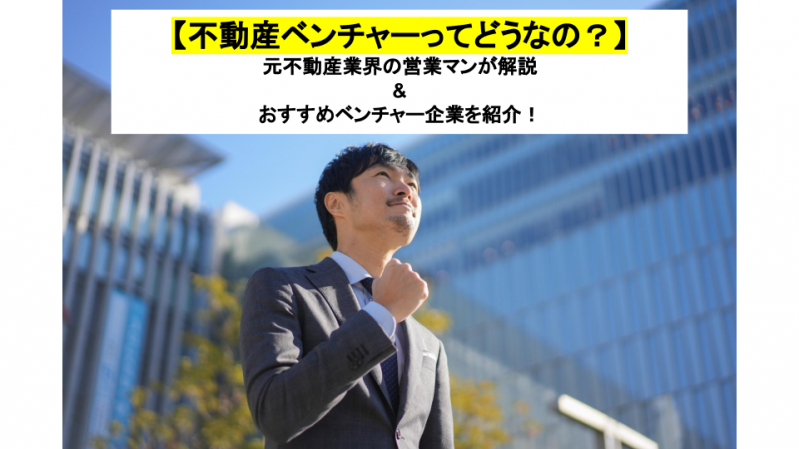【就活を始めたばかりの学生必見!】効果的な業界研究のやり方とポイントを徹底解説!
就活を始めるとき、「まずは業界研究をしましょう」といわれることが多いかと思います。
ただ、いきなり「業界研究」といわれても、何のためにするのか、具体的に何から始めればいいのかよくわからないという人も多いのではないしょうか。
そこでこの記事では、業界研究をスタートする人のために、業界研究の目的から流れ・方法、おさえるべきポイントにいたるまで、はじめての人にもわかりやすく解説します。ぜひ、最後まで読んでみてください。
- 就活における「業界研究」とは
- 業界研究の目的
- 業界研究の流れ
- 業界研究でおすすめの方法・ツールを紹介!
- 業界研究でおさえるポイント
- 業界研究のコツ
- おわりに
就活における「業界研究」とは
そもそも就活における「業界研究」とは、世の中にあるさまざまな業界やそこに属する企業への理解を深めるために行う活動です。
私たちが日々生活を送る中では、世の中にあるたくさんの業界のごく一部しか見えていません。小売業など、個人を相手に事業活動を行っている(BtoC)業界・企業のことはある程度わかっていても、システム開発や事業コンサルティングなど、企業を相手に事業活動を行っている(BtoB)業界・企業のことを知る機会はほとんどないからです。
一般消費者の目にはふれにくい業界や企業も多いからこそ、就活の際は業界研究をして「世の中にどのような業界が存在するのか」を知った上で、業界選び・企業選びをすることが大切なのです。
また、業界研究と自己分析と並行して進めることによって、「自分はこんなことに興味があるんだ」「こんな働き方がしたいんだ」といった、新たな気づきが生まれることも少なくないといえます。
業界研究の目的とメリット
業界研究の目的は「世の中にどのような業界が存在するのかを知る」ことだけではありません。
業界研究をすることで視野が広がり、当初は思いもよらなかった業界での就職が叶うかもしれません。また、自己PRや志望動機の作成など、選考のフェーズでも業界研究の成果を生かせるメリットもあるのです。
志望業界を絞る
業界研究の目的のひとつが「志望業界を絞る」ことです。世の中にはさまざまな業界があり、「この業界も良さそうだし、あの業界も面白そう」と、複数の業界に興味を持つ人も少なくないはずです。
色々な業界に興味を持つこと自体は素晴らしいですが、興味の対象があまりにも多い場合、すべての業界・企業の選考に応募するのは現実的ではないため、ある程度志望業界を絞る必要があるといえます。
したがって、業界研究を通して各業界の特性を知ることで、根拠を持って「この業界に興味がある」と言うことができ、自分に合った業界に絞ることができるでしょう。
視野を広げる
志望業界の絞り込みとは対照的に、業界研究は就活の「視野を広げる」ことにも役立ちます。
業界研究をしないと、興味の対象が日常生活になじみの深い業界や、知名度のある企業に偏ってしまいがちです。ところが、実は現時点では存在すら知らない業界や企業に、あなたにぴったりの「舞台」があるかもしれません。
その業界や企業の存在を知らなかったがゆえに、得られるはずのチャンスを逃してしまったら非常にもったいないと言えます。業界研究を通して知らなかった業界や企業の存在を知ることで、視野が広がり、結果的にチャンスも増えるでしょう。
説得力のある志望動機・自己PRを作成する
業界研究は、業界選びだけでなく選考対策にも役立ちます。「なぜその業界を志望するのか」「その業界・企業で自分がどのように活躍できるのか」など、説得力のある志望動機や自己PRを作成するには、業界の特性を深く理解している必要があるからです。
前提として、企業は自分たちと働いてほしい人材、自分たちの会社に貢献してくれる人材を探し、採用したいと考えています。そのため、自社の社風やこの業界に合っているか、そして企業が欲している人材であることをアピールすることが大切です。
業界研究が進み、志望業界への理解を深める段階になってきたら、「その業界で自分の強みをどう生かせるのか」「その業界ではどのような人材が求められているのか」なども意識しながら活動するといいでしょう。
パターン別 業界研究の流れ
業界研究の具体的な方法を紹介する前に、業界研究のおおまかな流れを確認しておきましょう。
業界研究は次のような流れで行うと、効率的かつ深く研究を行うことができます。ただし、絶対的な正解があるわけではないので、以下をベースにしつつ、やりやすいようにアレンジしてみてください。
1. 世の中にどのような業界があるのか、全体像を知る
業界研究の第一歩は、世の中に存在する業界の全体像を把握することです。まずは、大まかな業界の分類や、それぞれの業界がどのような役割を担っているのかを知ることから始めましょう。
例えば、製造業、サービス業、IT業界、金融業界などの代表的な業界の種類をリストアップし、それぞれの定義や特徴を簡単に調べてみるとよいでしょう。
この段階では、特定の業界に絞り込む必要はありません。広範な知識を得ることで、自身の興味や関心がどこに向いているのか、などといった新たな発見をすることが重要です。
2. 業界ごとの特徴をおおまかに知る
次に、全体像を把握した業界の中から、それぞれの業界が持つおおまかな特徴を掴んでいきます。具体的には、その業界の市場規模はどのくらいか、どのようなサービスや商品を提供しているのか、そして主な顧客層は誰なのかといった点に着目します。
BtoC(消費者向け)ビジネスが中心なのか、BtoB(企業向け)ビジネスが中心なのかを知るだけでも、業界の性質を理解する上で大きなヒントになります。
この段階で、興味が薄いと感じる業界は深掘りせず、自分にとって興味のある業界が何かを絞っていくようにしましょう。
3. 興味のある業界をさらに深掘りする
おおまかな特徴を掴み、興味を持った業界については、さらに深く掘り下げて研究を進めます。その業界は今後、成長が見込まれるのか、あるいはどのような課題を抱えているのかを調べてみましょう。
また、実際にその業界で働くことになった場合、どのようなやりがいを感じられるのか、一方でどのような厳しさがあるのかといった現実的な側面も重要です。さらに、その業界で活躍するためにどのようなスキルや人物像が求められるのかを把握することで、自己分析と結びつけるヒントを得ることができます。
4. 興味のある業界に属する企業について調べる
最後に、興味のある業界に属する具体的な企業について詳しく調べていきます。業界全体を理解した上で企業を調べることで、その企業が業界の中でどのような立ち位置にあり、どのような強みや特徴を持っているのかをより深く理解できます。
企業のウェブサイトや採用情報、IR情報などを確認し、事業内容、企業文化、求める人材像などを把握しましょう。これにより、自身のキャリアプランや価値観に合った企業を見つけることができるだけでなく、選考に進む際の企業研究にも役立てることができます。
上記のほかに、「興味のある企業が属している業界について調べる」「つきたい職種から業界を絞り込む」といったアプローチもあります。
主な業界一覧
業界といってもさまざまです。自分の興味のある企業がどこの業界に所属しているかチェックしておきましょう。
| 業界 | 主な内容 |
|---|---|
| メーカー | 農林、水産、建設、機械等 |
| 商社 | 総合商社、食品、アパレル、通販等 |
| 流通、小売業 | 百貨店、スーパー、コンビニ等 |
| 金融 | 銀行、証券等 |
| サービス、インフラ | 不動産、鉄道、航空、福祉、教育等 |
| ソフトウェア、通信 | インターネット、情報処理、ゲームソフト等 |
| 広告、出版、マスコミ | 放送、新聞、出版、広告、芸能等 |
| 他 | 官公庁、公社、団体 |
業界研究の方法・ツール
一口に「業界研究」といっても、その方法やツールはさまざまです。特定の方法やツールに偏ることなく、使えるものはどんどん活用しながら業界研究を進めていきましょう。
就活サイト・就活イベント
多くの就活サイトで「業界図鑑」「業界マップ」といった、業界研究に役立つ情報を発信しています。まずはこうしたコンテンツを活用して、世の中にどのような業界があるのか、全体感を把握しておくとスムーズに業界研究に取りかかれます。
また、就活サイトは業界研究に役立つセミナーなどのイベントを開催しているケースもあるので、イベント情報もチェックしておくとよいでしょう。
業界研究セミナー
その業界や企業に興味を持ってもらうため、就活サイトの運営会社や、実際に企業が「業界研究セミナー」を開催しているケースもあります。
企業が開催する業界研究セミナーは、その業界の最新の動向を学べるだけでなく、その業界で働くやりがいや厳しさなどについて、社員から生の声を聞くチャンスでもあるため、よりリアルな情報を得ることができるでしょう。
書籍・雑誌
ネットでの情報だけではなく、書籍や情報雑誌、新聞などの紙媒体の情報も、業界研究を行う上で利用できるツールです。
特に、『会社四季報 業界地図』という書籍では、180以上の業界と各業界の主要企業が掲載されており、業界の最新事情が大まかに理解できる書籍になっています。このような業界地図で全体像を把握した後、志望業界がある程度絞られてきたら、その業界に特化した情報誌などをチェックしてみるとよいでしょう。
また、日本経済新聞などの大手新聞でビジネス全般の動向を押さえた後、「日本流通産業新聞」「金融経済新聞」といった専門誌・業界紙で気になる業界の実情を深掘りしてみるのもおすすめです。
業界団体のホームページ等
多くの業界には、その業界に所属する企業が集まる業界団体が存在します。「○○業協会」「○○協同組合」「○○連合会」など名称はさまざまで、規模も大小あります。
必ずしも就活に役立つ情報が得られるとは限りませんが、ホームページや広報誌などで、その業界の現状などを発信している業界団体もあります。ほかではなかなか得られないコアな情報が手に入ることもあるので、チェックしてみる価値はあるでしょう。
OB・OG訪問
業界研究をするにあたっては、OB・OG訪問の機会も積極的に活用しましょう。
ある程度志望業界が絞られてきたら、業界研究を一段掘り下げて、仕事のやりがいや厳しさ、その業界で求められる人材などを知るフェーズに入ってきます。
こうした情報は書籍やインターネットよりも、実際にその業界で働いている人から得るのがおすすめです。OB・OG訪問でリアルな一時情報にふれることは、志望動機や自己PRの作成に役立つだけでなく、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
キャリアアドバイザーに相談
自分1人で業界研究をしていると、「これで本当に合っているのか?」「どこまで業界研究をすればよいのか?」など、誰かに確認や相談をしてもらいたいと感じると思います。
そこで、就活のプロであるキャリアアドバイザーを頼るのも一つの方法です。業界研究に役立つ情報やおすすめのセミナーなどを紹介してくれる可能性があります。加えて、面接練習や自己分析の方法など、就職活動に役立つアドバイスや選考対策も提供してくれます。
業界研究で抑えるポイントと注意点
なんとなく業界研究を進めていると、漫然とさまざまな業界の情報をインプットしているだけになってしまい、効果的な業界研究ができていない可能性があります。
そうならないためにも、以下のポイントをおさえながら業界研究を進めるようにしましょう。
業界の特徴や扱うサービスの形態を知る
世の中には数多くの業界があり、「モノをつくる業界」と「モノを売る業界」、あるいは「目に見えないサービスや情報を提供する業界」とでは、ビジネスのあり方が変わってきます。さらに、同じ「モノを売る」ビジネスであっても、一般消費者に売る場合もあれば、企業に売る場合もあります。
業界研究をするにあたっては、その業界が「誰」に対して「どのような価値」を提供しているのかを踏まえて、業界の特徴を理解するようにしましょう。
業界の成長性・安定性を知る
業界研究においては、業界の成長性や安定性も非常に重要なポイントです。年々市場規模が右肩下がりの業界と、まだまだ伸びしろのある業界とでは、当然後者のほうが長く活躍できる可能性が高いですし、業界や企業の成長とともに自分自身も成長できる余地が大きいからです。
業界の市場規模や推移、今後予測される社会の変化などを踏まえて、「その業界が社会全体でどのような位置づけにあるのか」「市場規模は拡大傾向にあるのか / 縮小傾向にあるのか」などに着目するようにしましょう。
業界の現状と課題をおさえる
業界研究では業界の魅力を知ることも大切ですが、客観的に現状を把握して、その業界の課題を認識することも大事になってきます。
業界が抱えている課題は、あなたがその業界に入ったときに取り組まなければならない問題である可能性が高いと言えます。そのため、「その課題に対してポジティブに取り組めそうかどうか」が業界選びのポイントのひとつになってくるのです。
また、面接などで「○○業界の課題は何だと思いますか?」といった質問を受けることもあるため、業界の現状と課題をおさえておくことは選考対策にもなります。
業界研究のコツ
自己流で業界研究を進めると、見方が一面的になってしまったり、使うツールに偏りがでてしまう可能性があります。
次の2つのコツを意識してバランスを取るように心がけてください。
「広く浅く」⇒「狭く深く」の順番で進める
業界研究をスタートしたら、まずは広く浅く、世の中にあるさまざまな業界について知るようにします。
特に、BtoBが中心の業界は私たちの日常生活になじみが薄いため、最初は興味が持てない人もいるかもしれません。しかし、知らないから興味がないだけで、少しでも知ってみると魅力的に映る可能性もあります。
だからこそ、最初の「広く浅く」知る段階では、できるだけ「食わず嫌い」をせず、さまざまな業界に視野を広げることを意識することが重要です。世の中にある業界の全体像を捉えることができた上で、興味のあるいくつかの業界を「狭く深く」知る段階に入っていきましょう。
さまざまなツール・手段を併用する
業界研究をするにあたっては、「使えるものは何でも活用する」という姿勢を持つようにしてください。
「インターネットだけに頼る」あるいは「家の中でできることだけをする」というのではなく、インターネット、書籍、新聞とさまざまな媒体を組み合わせるのはもちろん、セミナーやOB・OG訪問といったリアルな場にも出かけて、多角的な情報を得るようにするといいでしょう。
結局、家の中でできるリサーチで終わってしまうと、「その他大勢」が持っている情報しか得られません。セミナーに参加する、OB・OG訪問をするなど、積極的に外に出た人だけが得られる「生きた情報」があることを肝に銘じておきましょう。
関連記事:「就活で業界が絞れない」を解消!8大業界の特徴と業界研究のコツを知ろう
おわりに
業界研究は、志望業界を見極めたり、説得力のある志望動機や自己PRを作成したりするためにも非常に重要な活動です。加えて、社会のことを広く知れるチャンスであり、徹底した業界研究は入社後の社会人生活でも役立ちます。
「就活」や「業界研究」と聞くと、不安な気持ちや面倒な気持ちが先に立つ人もいるかもしれません。ところが、社会人になってからさまざまな業界のことを広く知る機会は意外と少ないもの。ぜひ「今まで知らなかった世界が見られる機会」と捉え、前向きに取り組んでいってくださいね。